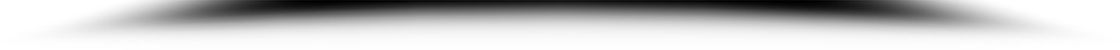打越弁財天とは
打越弁財天は、京王線の「北野駅」から徒歩で約15分の距離にあり、神社の周辺には、他にも多くの歴史的な神社や寺院が点在していて、地域全体が歴史と文化の薫る場所となっている。
すぐ側に八王子バイパスが通っており、参道入り口付近は少し埃っぽい印象だったが、一歩足を踏み入れればそこはやはり境界の向こう側。静寂そのもので、人ならざる者に出くわすのではないかという不安すら感じるほどである。
歴史
打越弁財天の歴史は古く、案内板によると開創は1573〜1591年頃で、室町時代の終わりから江戸時代初期という。同じ時期に起こった日本の歴史上有名な出来事といえば、1582年の本能寺の変だが、その時代に開創されたものだと言われれば、心熱くなり、重ねてきた時の流れに敬意の気持ちが芽生えるというものだ。
弁財天は、もともとインドの神であるサラスヴァティー(Sarasvati)を日本の神道に取り入れたもので、芸能や財運、学問の神として広く信仰されている。
打越弁財天の周辺を含む八王子はかつて、織物の街として養蚕業が栄えていた。近隣の養蚕業を営む家庭では、蚕を「お蚕様」と呼び、人間よりも大切にされていたそうだ。そうして大切に育てた繭をネズミに荒らされては敵わないということで、「白蛇を御神体とする弁財天信仰が盛んになった」(「打越弁財天」境内案内板より)ということだ。
アクセス
| 所在地 | 〒192-0911 東京都八王子市打越町 |
| アクセス | 京王線「北野駅」より 徒歩約15分 |